<<次世代不動産経営実務者養成カレッジ第4期 by次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー>>
都市の新たなイノベーション
『オンリーワンのチャレンジで、都市の新時代を創るひとたち』
不動産業界において大きな変化が起こりつつある。そうした中、「不動産オーナー井戸端ミーティング」を主宰する𠮷原勝己オーナー(福岡市)が中心となり、貸し手と借り手、そして地域にとって「三方よし」となる、持続的でブランディングされた不動産経営を目指す勉強会を有志で開催している。
当連載では、建築・デザインを学ぶ学生たちと、全国から集まったプロフェッショナルが一緒に受講する場として、九州産業大学建築都市工学部で行った全14回の「不動産再生学」と題した寄附講座を紹介。今回は、空き家や廃業施設の再生を通じて地域活性化を実現するDesign Space(鹿児島県伊佐市)の脇黒丸一磨氏の講演をレポートする。
Design Space(鹿児島県伊佐市) 代表社員 脇黒丸 一磨氏
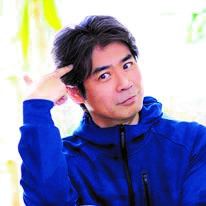
伊佐市でのビジネス:空き家再生から始まった地域活性化
私の活動フィールドは鹿児島県伊佐市です。鹿児島県と熊本県の県境に位置しており、冬は「鹿児島の北海道」と言われるほど寒く、マイナス5度からマイナス6度まで下がります。一方で、夏は30~40度まで上がる地域です。妻の出身地だった縁で伊佐市に移住したのですが、本当に「何もないところ」でした。しかし、この「何もない」という状況に、私は大きなビジネスチャンスを感じ、10年以上事業を展開しています。
私の本業は橋梁設計士ですが、現在、複数の会社の経営と10事業を展開しています。これは、スタッフの困りごとを解決していった結果です。私の企業理念・ビジョンは「次世代に残す企業」。社会や地域が抱える問題点や必要なものを事業として立ち上げ、つくり出すことを得意としています。社名「Design Space(デザインスペース)」には、社員一人ひとりが自分の人生をデザインできるような「場所」をつくりたいという願いが込められています。そして、この多岐にわたる事業の根幹には、全て「不動産」が基礎として存在しています。不動産がなければ、これらの事業は成り立ちません。
経営学を専攻していた大学時代は、正直に言って一切勉強はしませんでした。アルバイトや個人事業主としてさまざまな事業を立ち上げ、稼いだお金を車に投資して遊んでいました。決して学業が優秀でなくても、行動すれば道は開けるということを私は身をもって体験してきました。
私の不動産の世界への関わりのきっかけは2011年。世間で「空き家」という言葉がまだ流行していなかった頃に「何か使えないか」「お金をかけずに活用する方法はないか」と考えたことでした。これが私の「スタートライン」です。
空き家・廃墟の活用:アイデアと行動力で新たな価値を創造する
不動産事業に関しては、廃墟住宅や廃業施設を活用することが主な仕事です。田舎では空き家がどんどん増えており、問題だと感じていたので、そういう事業を展開できないかと思い、再生を始めました。
伊佐市のような地方では、廃墟となった社宅、空き倉庫、廃業したスーパーマーケット、古民家、廃業施設など、使われなくなった不動産が「超マイナーな」問題として山積しています。私の仕事は、これらの「眠れる資源」をどう活用するかです。
私はファーストステップとして、まず空き家を見つけ、家主からタダで借り、それを転借・転売する「スモールビジネス」、すなわち「0円不動産」を始めました。これは、お金をかけずにできるため、誰にでも挑戦できるビジネスモデルです。しかし「簡単だ」と言いつつも、実際に踏み出す人の9割が途中でやめてしまいます。私は、残りの1割に入って行動したからこそ、今の事業があります。「借りて貸す」を100件以上繰り返し、1件あたり2~3万円の収入を得ることで、それを新たな事業の「種」としてきました。世の中には、手を入れなくても貸せるような物件もごろごろ転がっているのが現実です。

次に手がけたのは、企業が地方から撤退したことで残された「廃墟社宅」の再生です。これらは質の良い内装や構造の物件が多く、先述の0円不動産で得た収益を元手に安価で買い上げ、リノベーションして貸し出すことで、次のステップへとつなげていきました。誰も手を出さない物件をリノベすることで、利回り40%を達成した事例もあります。
「空き倉庫活用」も重要な取り組みです。廃業した薬局の倉庫など、撤退する企業から安く仕入れた倉庫をそのまま貸し出すのではなく、用途を変えて活用しました。 まず、1階ではマルシェを開催。これは、伊佐市に眠るハンドメイド作家を発掘し、彼女たちのPRの場とするためです。このマルシェを通じて、魅力的な作家さんや出店に興味がある人を見つけ出し、彼らを私が所有する別の物件(例えば商店街の店舗など)のテナントとして迎え入れることを目指しました。2階部分はシェアオフィスの形で整体、ネイル・まつ毛エクステンション、ストレッチ・ヨガ教室などの事業者が自由に出入りできるスペースとしました。ここでも、マルシェで見つけた人々や、これらの活動を通じて知り合った人々を、最終的には私が持つ商店街の店舗へと誘導するビジネススキームを構築しています。
さらに、国の企業主導型保育事業の募集を知り、進出することにしました。倉庫の1階を保育園施設につくり変えて運営しています。社会貢献として会社のイメージを向上させるこの事業では、市役所や行政と連携して地域の子どもたちの受け入れをしています。
「廃業スーパーマーケット活用」の段階になると、こちらから物件を探しに行かなくても、オーナーから「これを使ってくれないか」「どう活用できるか」という相談が持ち込まれるようになりました。これも、倉庫と同様に企業主導型保育園として活用しています。 ここでの重要な視点は「御用聞き」です。地域やお母さんたち、子どもたちが何に困っているのか、地域の「問題」を解決していくことこそが、最もビジネスとしてつながりやすく、人間関係もしっかりと築くことができるのです。
自分がやりたいビジネスを闇雲に押し進めるだけでは、失敗する確率が格段に上がってしまいます。地域の声に耳を傾け、地域の問題を解決することが、共感を生むビジネスにつながるのです。伊佐市は高齢化率が60%を超える高齢者社会です。80歳以上になると強制的に運転免許証の返納を求められるため、バスも電車も通っていない地域では買い物に行けないという問題に直結します。そこで、私は安価な物件を買い集め、そこで弁当を作り、地域に届けるという高齢者支援事業を始めました。これは「お惣菜屋」という形での廃業スーパーマーケットの活用にもつながっています。

ほかにも、廃業した高齢者施設の居抜き物件活用を行っています。国の制度の難しさや、職員の離職などで多くの高齢者施設が運営に行き詰まり、潰れていくという深刻な問題が地方では起きています。しかし、高齢者施設を新たに始めるには、多大な設備投資が必要です。そこで、私は設備が整ったまま潰れてしまった施設に着目。設備投資をせずにそのまま運営できる方法を選びました。さらに、その施設で職を失った職員をそのまま引き抜き、別の居抜き物件で再雇用するのです。私は高齢者施設の知識は全くありませんが、知識を持ったスタッフが運営してくれるため、新たに勉強する必要はありません。これは「人材M&A」と呼ばれるやり方で、今後都市部でも増えてくる重要な手段だと考えています。
私の考える不動産再生の理念
不動産再生とは「地域・エリアの問題を解決することで、事業を成り立たせ、それぞれがWin-Winとなることを目指す」と考えています。地域に残された資源を今ある事業とつないで、新しいオンリーワンを創造していく。そして何よりも重要なのは「行動に移す勇気と決断」です。
最初は不動産再生で得られる家賃収入や販売益といった「見える資産」に注目していました。しかし、事業を進めるうちに「見えない資産」の重要性が見えてきたのです。それは「人材」「事業」「プロジェクト」、そして「社会貢献」へとつながっていきます。単に空き家を活用し、家賃収入を得るだけでなく、そこに一つ工夫を加え、人財育成や新たなプロジェクト、事業の展開、さらには教育や社会問題の解決といった「社会のための不動産再生」へと裾野を広げることができる、唯一の手段だと確信しています。
行動こそがオンリーワン
私が皆さんに伝えたいのは、どんなに素晴らしいアイデアがあっても、行動を起こさないことには何も生まれないということです。もちろん勉強は非常に重要ですが、その先の行動こそが、オンリーワンになれる最も早い道だと信じています。
先日、北海道でサイクルツーリズムやアドベンチャーツーリズムを推進されている高橋幸博氏とお話する機会がありました。高橋氏のグローバルな視点と、お金を持った外国人観光客を誘致する手腕には大変刺激を受けました。私はこれまで伊佐市というフィールドからあえて出ずに活動してきましたが、高橋氏のような人と連携することで、伊佐市に新たな人の流れや、これまでにないイノベーションを起こし、人材育成にもつながるのではないかと、今から非常にワクワクしています。私の持つ地域の「点」となる事業(米作りやサバイバルゲーム場など)が、高橋氏のサイクリングツアーの立ち寄り先としてつながる可能性も感じています。
今の日本は大きな組織だけでなく、個人のプロフェッショナルでも新しい時代を創り出すことが可能になっています。私や高橋氏は、裏方として場を調整し、人々や地域をつなぐことで大きな影響を生み出しています。ビジネスの成功に大切なことは、一歩踏み出し、多くの人々とつながり、自分に与えられた仕事や縁を大切にしつつ前向きに挑戦し続けることです。
若い皆さんが抱える「やりたいこと」は、チャンスに満ち溢れています。SNSでは、投資したいと考えている人たちが面白いネタを探していますし、若い人手が本当に必要とされています。まずは小さくても良いので行動を起こし、地域の問題解決につながるような事業に挑戦してみてください。行き詰まった時や、さらなる可能性を広げたい時は、いつでも声をかけてください。私自身、若い皆さんと一緒にフィールドで「馬鹿なこと」をするのが大好きなのです。
(2025年7月公開)
関連記事↓
電子版:不動産再生学講座 第4講:観光で地域の価値向上
















