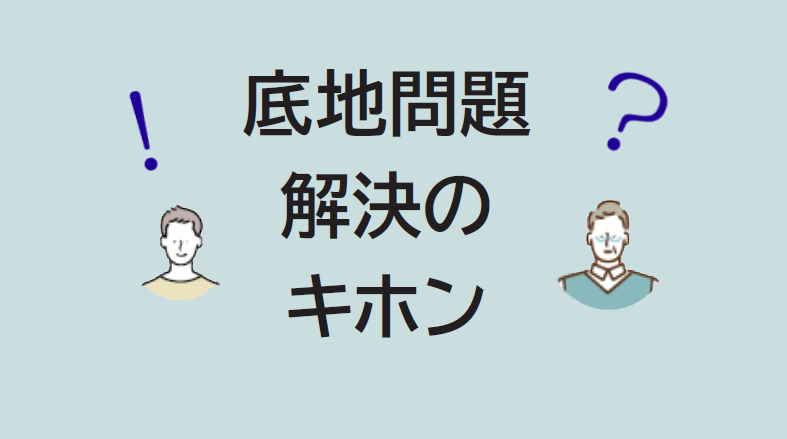<<次世代不動産経営実務者養成カレッジ第3期 by次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー>>
建築・再生から始まる新時代イノベーション
不動産の建築・再生から、次世代不動産のビジョンと価値を創るひとたち
不動産業界において大きな変化が起こりつつある。そうした中、「不動産オーナー井戸端ミーティング」を主宰する𠮷原勝己オーナー(福岡市)が中心となり、貸し手と借り手、そして地域にとって「三方よし」となる、持続的でブランディングされた不動産経営を目指す勉強会を有志で開催している。
当連載では、建築・デザインを学ぶ学生たちと、全国から集まったプロフェッショナルが一緒に受講する場として、九州産業大学建築都市工学部で行った全14回の「不動産再生学」と題した寄附講座を紹介。今回は、熊本地震の影響による建物解体後の「場づくり」を通して商店街に新しい価値を創造する面木健氏の講演をレポートする。
オモケンパーク 面木 健氏(熊本市)

商店街のあり方を見つめ直す
オモケンパークは、熊本地震で被災し解体を余儀なくされたビルの跡地にシェア拠点をつくるプロジェクトによって生まれました。現在は、市民のさまざまな活動を支援する多目的スペースとして活用されています。
私は1965年生まれで、熊本市のアーケード商店街である上通で生まれ育ちました。普段は会社員をしながら、この街で「場づくり」に情熱を注いでいます。私がずっと考えているのは、今の「マチ」、特に商店街のあり方で本当にいいのかということです。インターネットで何でも買える時代において、ただモノを売買する店が連なる商店街に、どれほどの魅力があるのだろうかと。またアーケード商店街というと、どうしても建物の「ファサード(正面)」だけが整えられて、その奥にある土地の奥行きや、建築そのものを楽しむことができないのではないか? これが、私がこの活動を始める原点です。
日本の人口は20年連続で減少しています。毎年70万人から80万人ものペースで減っているのです。熊本市が約73万人ですから、毎年熊本市程度の人口が全国で消えている計算になります。だからこそ、私は「拡大・成長」から「縮充・成熟」へという考え方を提唱したいと思っています。「増やす先に幸福はない。減らす先にしか幸福はない」と、私は強く感じています。「右肩上がりをもう一度」ではなく、「右肩下がりをポジティブに生きよう!」と、私は自分の取り組みを通して伝えたいと思っています。
震災をきっかけに一念発起

私の人生の大きな転機となったのは、2016年の熊本地震でした。上通にあった築100年の実家兼テナントビルも大規模半壊し、17年2月には解体せざるを得なくなってしまいました。残されたのは、幅6m、奥行き30mの更地と、昔からあった井戸だけでした。震災後、テナントビルを再建することも考えました。しかし、当時の3階建ての建築費用は2億円にも膨れ上がっていて、30年前の7,000万~8,000万円とは比べ物になりません。これを25年ローンで返そうとすると、月に100万円もの返済が求められます。震災直前の1階の家賃が85万円だったことを考えると、空室リスクも増す中で、とても採算が合うとは思えなかったのです。
この状況に、私は「なんだか違和感がある。このままだとまずいぞ!」と直感しました。多額の借金を背負って、熊本のローカル色が薄まるような方向へ進むことは、私の人生の選択肢としては考えられませんでした。
震災直後、街中で見た光景が忘れられません。店はシャッターを下ろしていても、人々は中心部に出てきて互いを励まし合っていました。その時、「人々が出合い、心を交わす場」こそが、この街の本当の魅力だと確信しました。「お金よりももっと大切なものがあるはずだ」と。だから、私は「この街に住んでいてよかった!」「この街に来てよかった。また来たい!」と誰もが感じることができる街にしたい、まず自分の場所から目指そう、と決心したのです。
場づくりはあえて「小さな建物」で

「更地になってもできることは何か」。そう考え、17年7月から約1年4カ月にわたって、私は「場づくり」の社会実験を始めました。建築家でありアーティストでもある坂口恭平氏や、解剖学者で多くの著作を持つ養老孟司氏を招いた「モバイルハウス計画」を始め、土木学会の「どぼくカフェ」、慶應義塾大学との連携、古着フェス、フードカー、ストリートアート、ジャズイベントなど、本当に多様な試みをしました。 この実験を通じて、私は「建物がなくてもワクワクすることはできる!」「場はつくれる」という確信を得ました。
そして、建物づくりを考えるなら、デンマークの建築家、ヤン・ゲール氏が提唱する「アクティビティ→空間→建築」という順序でプラニングすることの大切さを痛感したのです。彼の著書『人間の街』を読んだ時、私が感覚的にやってきたことが、アカデミックに書かれていることに驚きました。
この確信に基づいて、私は「オモケンパーク」の建設に着手しました。掲げたのは「ダウンサイジング」です。指定建蔽率80%に対し35%、指定容積率600%に対し25%という、とんでもなく低い割合で建てることで、既存の不動産開発へのアンチテーゼを示したかったのです。 建設には、CLT(クロスラミネーテッドティンバー)工法という新しい技術を取り入れました。そして、熊本の象徴である豊かな地下水が湧き出る「井戸」を最大限に活用し、阿蘇の溶岩石や地域の木材など「熊本の素材」を多用しました。一番こだわったのは、「売り手、買い手という関係ではなく、誰もが『市民』として活動できる場所をつくろう!」と考えて、自分たちで運営するスタイルを選んだことです。

(2025年8月公開)
次の記事↓
電子版:不動産再生学講座 第4講:世代を超えた人々が集まる場づくり