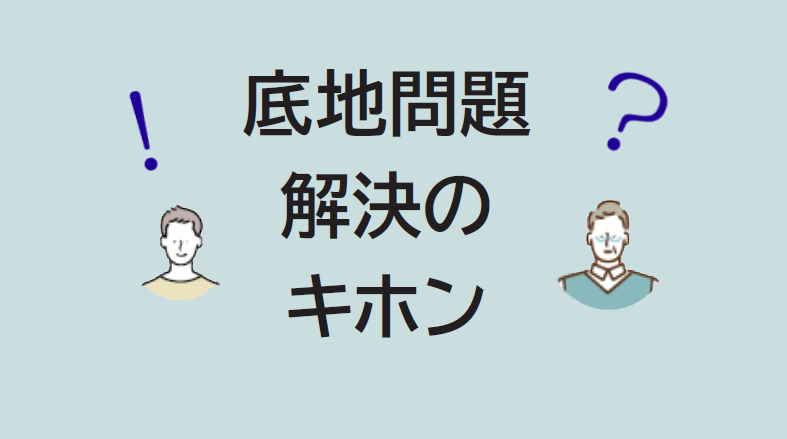<<次世代不動産経営実務者養成カレッジ第3期 by次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー>>
建築・再生から始まる新時代イノベーション
不動産の建築・再生から、次世代不動産のビジョンと価値を創るひとたち
(1)に続き、九州産業大学建築都市工学部で行った全14回の「不動産再生学」と題した寄附講座から、熊本地震の影響による建物解体後の「場づくり」を通して商店街に新しい価値を創造する面木健氏の講演をレポートする。
場の魅力を「チーム」で最大化する
2019年6月のオープン以来、オモケンパークでは多様なイベントが開催されてきました。オープニングレセプションから、リノベーショントーク、高校・大学連携プロジェクト、子どもたちが地下水に親しむ井戸の周りのプールイベント、各種展示会、クロストーク、ラグビーワールドカップ関連イベント、持続可能なクリスマスツリーや門松の設置、餅つきなど、地域に根ざした活動を大切にしています。
私の哲学は、「個人→チーム→社会」へと段階的に広がっていきます。まず「個人」として、私のライフスタイルや考えを地元紙のコラムや大学の建築学科の学生、小学校長への講演などを通じて発信しています。次に、この「オモケンスタイル」を「チーム」で共有することに力を入れています。「場の魅力を最大化」「働きたくなる場をつくる」「スタッフ自らが考え楽しむ」を目標に掲げています。
スタッフミーティングを兼ねて熊本県の江津湖で遊んだり、地元食材を使ったクリエイティブな料理の試食会をしたり、年1回のスタッフ旅行に行ったりと、「場づくりマインド」を共有するんです。スタッフにも積極的に発言の場を与え、個性を尊重したチームビルディングを行っています。そして最終的に、「オモケンスタイルに共感するファンをつくる」ことで「社会」と共有することを目指しています。お客様に心から向き合い、「やりたい気持ち」を応援し、私たちスタッフも参加者である、という姿勢を大切にしています。

その成果は、少しずつですが形になってきています。星野リゾート(長野県軽井沢町)の「OMO5熊本」が開業後、うちの井戸の価値が注目され、海外からの宿泊客を連れてくる街中ツアーに組み込まれるようになりました。崇城大学建築学科の古賀研究室が、リアルなオモケンパークをメタバース空間に再現し、そこでイベントを開催する試みもしてくれました。障がい者が一日カフェの店員になる企画など、福祉関係の団体が主催するイベントも積極的に応援し、多様な人々が街を楽しむ場を提供できています。若い世代が自身のプロジェクトを発表する場を提供したり、「恋する上通」と題した婚活イベントを開催したりと、新たな出会いや挑戦を応援するプラットフォームにもなっています。

世代を超えた意志の継承
特に喜びを感じるのは、イベント参加者からの「ここでやってよかった」「またやりたい」「新たな出会いがあった」といった感想です。忘れられないのは、90歳のおばあちゃんが言ってくれた「ここにくると昔の上通を思い出すとたいねー」という言葉。今の若い人が「おしゃれですね」と言ってくれるのも嬉しいですが、おばあちゃんの言葉は私の目指す「世代を超えてバトンをつなぐ」街づくりの核心を表しているように思えるのです。
先日、私の亡き父が50年前に街中に木や広場をつくりたいと語っていた新聞記事が、父の書斎から出てきました。これを見た時、私がやっていることが、世代を超えた意志の継承であることに鳥肌が立ちました。親や先祖への尊敬を忘れず、でも「自分の時代は絶対来る」という覚悟と責任を持って、自分らしいスタイルで未来を築いていくことの重要性を、私はこれからも伝えたいと思います。

右肩下がりをポジティブに生きる
私の取り組みは、日本が直面する人口減少時代において「右肩下がりをポジティブに生きよう!」という力強いメッセージを体現しています。「増やす先に幸福はない。減らす先にしか幸福はない」という言葉は、従来の「拡大・成長」モデルからの脱却を示唆しており、まさに「縮充・成熟」の時代を生きるための指針だと信じています。
しかし、その道は平坦ではありません。もちろんアーケードにはオモケンパーク以外にもさまざまなテナントやオーナーがいらっしゃり、そういった街の人たちの理解を得るためにはいろいろな苦労もあります。これは、私のオープンな「場づくり」が、商店街の快適性という別の価値とぶつかっている状態です。これは、私の挑戦が「第二章へ続く」ことを示唆しているのだと思います。来年には私も60歳になり、サラリーマンとしての収入もなくなります。オモケンパークという場所をどう持続させていくのか。これは、私自身の個人的な課題であると同時に、日本の地域再生における普遍的な問いでもあります。
私の「場づくり」は、単なるビジネスモデルではありません。熊本地震という逆境を乗り越え、地域と未来への深い愛情と覚悟を持って、新たな「幸福の形」を創造しようとする、私自身の生き様そのものなのです。建築や不動産が、いかに人々の暮らしや心、そして社会の在り方を変え得るか。その可能性を信じて、これからもこの場所で挑戦を続けていきたいと思っています。
(2025年8月公開)
関連記事↓
電子版:不動産再生学講座 第4講:大規模半壊した実家兼テナントビルを再生