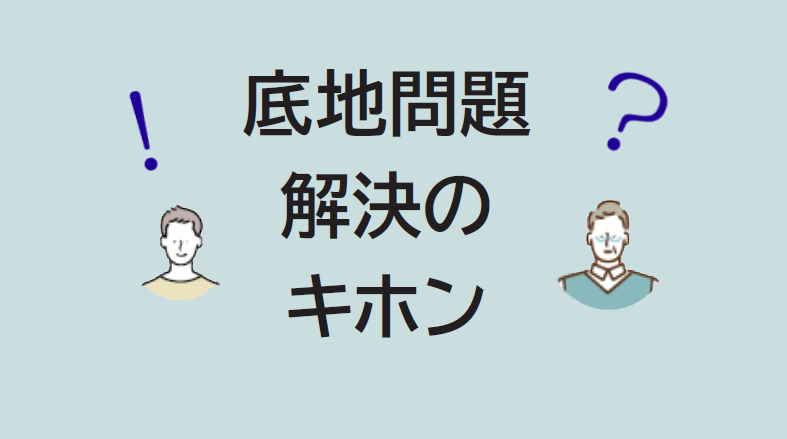<<次世代不動産経営実務者養成カレッジ 第3期 by次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー>>
団地再生から始まる新世代生活
『いにしえの団地から、新たな次世代団地を創るひとたち』
不動産業界において大きな変化が起こりつつある。そうした中、「不動産オーナー井戸端ミーティング」を主宰する𠮷原勝己オーナー(福岡市)が中心となり、貸し手と借り手、そして地域にとって「三方よし」となる、持続的でブランディングされた不動産経営を目指す勉強会を有志で開催している。
当連載では、建築・デザインを学ぶ学生たちと、全国から集まったプロフェッショナルが一緒に受講する場として、九州産業大学建築都市工学部で行った全14回の「不動産再生学」と題した寄附講座を紹介。今回は、「団地愛好家」として団地が持つ未来への可能性を発信する有原啓登氏の講演をレポートする。
地方住宅供給公社・団地愛好家
有原啓登氏(大阪府)
団地の大量供給 ― 住宅不足解消の切り札
大学などで講演する際、「団地に住んだことがある人はいますか?」と尋ねても、手が挙がることはほとんどありません。しかし、私と同世代である1970年代頃に生まれた団塊ジュニアは、多くが団地での暮らしを経験しています。私も団地生まれです。若い人々の視界からは少し消えてしまったかもしれない「団地」ですが、実はそこには学ぶべきことがたくさん詰まっています。そこでまず、古い団地が持つ独特の面白さについてお話ししたいと思います。
そもそも団地は、第二次世界大戦後の深刻な住宅不足を解消するために誕生しました。戦争によって住宅建設は停滞し、多くの家が焼失しました。戦後10年経っても全国で約284万戸もの住宅が不足するという、今では想像し難い状況だったのです。この国家的課題を解決するため、短期間で大量に住宅を供給する必要がありました。
そこで生み出された一つが「標準設計」という考え方です。特に「51C型」と呼ばれる2DKの間取りは、あらかじめつくられた図面を全国の公営住宅設計時に利用することで、建設のスピードを飛躍的に向上させました。全国の団地がどこか似たような姿をしているのは、このためです。
建設が本格化した当初は、技術的な制約も多くありました。例えば、土地を造成するための重機です。今でこそショベルカーやブルドーザーは種類も多く高性能ですが、当時は馬力が十分でなく、しかも外国からの輸入品しかありませんでした。そのため、大規模な造成が難しかったのです。旧日本住宅公団(現在のUR都市機構)が建設した「千里青山台団地」には、工夫が見られます。一般的な長方形の住棟ではなく、正方形に近い「ポイントハウス型」と呼ばれる住棟が採用されていますが、これは造成工事を最小限に抑えるための知恵でした。

また「住棟配置」にも設計者たちの情熱が注がれました。多くの団地では、すべての住戸に平等に太陽の光が当たるよう、住棟を南向きに平行に並べる「南面並行配置」が採用されました。こうすることで最も日当たりの悪い冬至の日でも、最低4時間は日照が確保できるよう計画されたのです。しかし、設計者たちはそれだけでは満足しませんでした。内部の図面は標準化されていて個性を出しにくいため、住棟をコの字型に配置して中庭を作ったり、少しずつずらして囲み型の空間を創出したりと、配置計画で腕を振るったのです。
ここで少し、「団地」の定義について触れておきましょう。一言で団地と言っても、所有者によって種類が異なります。UR都市機構(旧日本住宅公団)によるUR賃貸住宅、地方住宅供給公社による公社団地、地方公共団体による公営住宅、そして民間企業が分譲した団地型マンションなどです。大阪の千里ニュータウンでは、建物の表示に「A」や「B」といったアルファベットが振られていますが、これは事業主(大家)が誰であるかを示しています。ただし、この方法は住人のコミュニティー形成に好ましくないとの意見から、後のニュータウンではあまり採用されなくなりました。
古い団地の例として、大阪府住宅供給公社の「豊津団地」を紹介します。1951年(昭和26年)に建設された、今も現役で人が暮らす最も古い団地の一つです。この団地にはベランダがなく、洗濯物は屋上の共同物干し場で干します。さらに各戸に風呂はなく、1階にある共同浴場を現在も使っています。2016年には関西大学の学生が居住実験を行い、団地を知らない若い世代がその暮らしを体験するという試みも行われました。

団地の高層化と多様化
昭和30年代に入ると土地の取得が困難になりますが、より多くの住戸を確保するため団地は高層化の時代を迎えます。よく知られるのは、兵庫県の「芦屋浜高層住宅」です。これは、工場で作ったプレハブの住居ユニットを鉄骨の構造体に組み込んでいくという、当時としては画期的な工業化工法で建設されました。国や自治体、企業が団結して取り組んだ、まさに国家プロジェクトでした。また、大阪の泉北ニュータウンにある「晴美台D団地」と「槇塚台団地」は、かつて道路をまたぐ約200mのブリッジで2つの団地が結ばれ、屋上には公園までありました。都市計画的な視点から生まれた、非常にスケールの大きな団地です。
1973年頃には住宅不足がほぼ解消されます。さらにオイルショックによる低成長期に入ると、大規模開発や高層化への反省も生まれ、「住宅は量から質へ」と価値観が転換します。この時期からデザイン性の高い団地や、住まい手のライフスタイルに合わせた住居がつくられるようになりました。例えば、1999年に建設された「ふれっくすコート吉田」は、スケルトン・インフィル(SI)という手法を採用した賃貸団地です。これは柱や梁などの構造体(スケルトン)と、内装や設備(インフィル)を別々につくる考え方で、住む人が間取りを自由に変えられるのが特徴です。賃貸団地でこの手法が採用されたのは非常に珍しく、画期的な試みでした。

次世代団地の将来性とは
建設から約50年が経過し、団地は新たな課題に直面するようになりました。一方で、そこには未来への大きな可能性があります。
まず、古い・狭い・設備が陳腐化しているといった理由で、団地は住まいとしての魅力を失いつつあります。そこで注目されているのが、既存の建物を活かす「ストック活用」、つまりリノベーションです。古さと新しさを併せ持つことで、若い世代にもアピールしようという動きが全国で始まっています。大阪の「喜連団地」では、若年層の入居を促進するため、外壁を茶色ベースに赤や黄色の差し色で塗装し、大胆なイメージチェンジを図りました。大阪らしい派手さですが、駅前の商業地に近いため街の賑わいに溶け込んでいます。

また、住人の高齢化も深刻な課題です。団地は単に「住む場所」だけでなく、「福祉的な機能」も求められるようになりました。愛知県の「大曽根住宅」では、空き家を分散配置する形で「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」として活用しています。これにより、高齢者ばかりの施設ではなく、子育て世帯など多世代が混在する中で暮らすことができ、心理的にも良い影響を与えています。大阪の「OPH杉本町」では、空き住戸を地域の孤食を支援する食堂「みんな食堂」に改修しました。この食堂は障がい者福祉作業所と連携しており、障がいのあるスタッフが調理や接客を担当しています。孤食になりがちな高齢者が集い、経験豊かな高齢者が障がいのある若者を支えるという、優しい関係性が生まれています。
さらに、かつては若い入居者が多く団地祭りで賑わった団地も、今では高齢化や空き家の増加でコミュニティーが希薄になっています。しかし、この課題にこそ団地再生のヒントがあります。大阪の泉北ニュータウンにある「茶山台団地」では、複数の取り組みが同時多発的に行われているのが特徴です。使われなくなった集会所を住人がDIYで改装した「茶山台としょかん」、団地内の食堂「やまわけキッチン」、斜面地を活用した「レモン畑」、2住戸を1つにつなげたリノベーション「ニコイチ」など、多彩な活動が展開されています。担い手も住人、NPO、民間事業者、大学などさまざまです。これにより、住人は自分の興味に合わせて関わり方を選ぶことができ、担い手同士も協力し合えるという相乗効果が生まれています。これからの賃貸住宅経営では、単に部屋を貸すだけでなく、魅力的な暮らしの体験そのものを提案することが重要になってくるでしょう。

私たちは何を応用できるか
団地は戦後の住宅不足という国家的課題を解決するために、先人たちが知恵を絞り、海外の事例を研究し、新しい理論や技術を次々と生み出してつくられました。その情熱と工夫の歴史から学ぶことは非常に多いはずです。
多くの人が集まって暮らす団地は、社会の課題が最も早く現れる場所です。住宅不足に始まり、建物の老朽化、住人の高齢化、コミュニティーの希薄化など、「団地は日本社会の縮図」と言えます。だからこそ団地で起きていること、そしてそこで行われているさまざまな再生の取り組みに目を向けることで、これからの都市や街が直面する課題を解決するヒントが見つかるはずです。つまり、「団地は都市課題の先行指標」なのです。
団地は「全国画一的」と揶揄(やゆ)されることもありますが、それは裏を返せば、一つの成功事例がドミノ式に全国の団地へ波及していく可能性を秘めているということでもあります。ある地域での取り組みが、他の地域の課題を解決するイノベーションになるかもしれません。
皆さんがこれから学ぶ、あるいは実務で取り組む不動産再生の試みが、いつか日本の社会課題を解決する大きな力になる可能性があります。次の時代のイノベーターは、皆さん一人ひとりなのだと私は信じています。
(2025年9月公開)