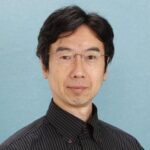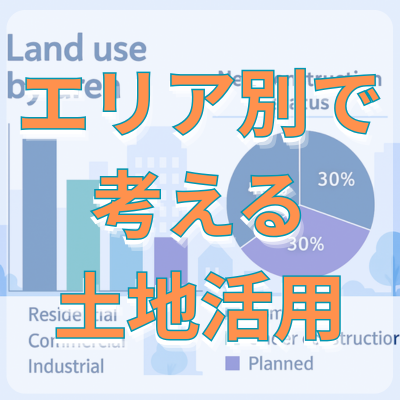- HOME
- 賃貸経営
- リフォーム・リノベーション
- 【電子版連載】次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー:特別座談会(1)
「場のデザイン」から「共感不動産」を考える
相次ぐ自然災害や資材価格の高騰などの影響により、大きな変化が起こりつつある不動産業界。そうした中、「不動産オーナー井戸端ミーティング」を主宰する𠮷原勝己オーナー(福岡市)が中心となり、貸し手と借り手、そして地域にとって「三方良し」となる、持続的でブランディングされた不動産経営を目指す勉強会を有志で開催している。今回は、第二弾カレッジ「場のデザインから共感不動産を考える」を総括して、九州産業大学准教授・信濃康博氏 、スペースRデザイン・本田悠人氏、𠮷原勝己オーナーの3者で実施した座談会を全6回にわけてレポートする。
- 九州産業大学 建築都市工学部 准教授 信濃康博氏
- スペースR デザイン(福岡市) 本田悠人氏
- 𠮷原勝己オーナー(福岡市)
*** リノベーションと文化的社会的背景 ***
𠮷原:共感不動産というコンセプトは、20年以上におよぶリノベーションの経験から導き出された、まさにサステナブルな不動産再生のモデルとも言えます。不動産経営におけるビジョン、デザイン、そして日々のオペレーションを一つの三角形として構成し、その上に時間のデザインを加えて4次元構造にするという視点は、現代の不動産再生における、普遍的な仕組みではないかという実感がわいてきました。
今回はリノベにおける場のデザインが、不動産再生という文脈で社会的・経済的にどのような影響を与えてきたかについて議論できればと思っています。
――共感不動産という概念が長年の取り組みの中で、徐々に明確化されてきたようですね。場のデザインにおいて「共感」の要素がどのように形作られてきたのか、またその共感は普遍的なものなのか、それとも時代に応じて変化してきたのか、という点はまさに今回の取り組みの核心に迫る要素だと思います。
信濃:2000年頃に、日本で同時多発的にリノベの流れが始まったように思います。また戦後に欧米の文化が入り込み、皆がファッションに興味を持ち始めた流れが、その後に住宅や生活空間にも波及していったという背景がありますね。
しかし、住宅不足が長く続いていた時代には、賃貸住宅に手を加えることが許されず、大きな変化はなかなか生まれませんでした。それがバブル崩壊後の1990年代終盤からリバイバルブームが起こり、特に60年代のミッドセンチュリー文化やヴィンテージスタイルが若者の間で再評価されるようになりました。そのようなノスタルジックな動きが、団地やヴィンテージビルなどを魅力的に感じる風潮と結びつき、2000年頃から本格的なリノベの流れが始まったように思います。
𠮷原:確かに、投資型マンションの背景には「確実性」という要素が強く、全国どこでも同じようなデザインのものを提供すれば、安定して入居者が入るという前提がありました。そのため、住む人が部屋の個性を求め、ファッションや家具、装飾などを楽しみたいというニーズが長い間不動産業界によって無視されてきたのですね。しかし、そのニーズは潜在的に存在していて、実際には多くの人が自分らしさを反映した住まいを求めていたのだと思います。
信濃:そこに目をつけたのが、一部の感度の高いデベロッパーや設計者、そして不動産業者です。古いマンションでも、少しリノベを施せば個性を求める人たちが興味を示し、入居してくれるという事実に気がつきました。
元々、住む側「住まいを貸してください」という受け身の姿勢しか持てなかったのですね。家主が一方的に条件を決め、賃料を払って借りるというビジネスモデルでした。しかし、老朽化した建物が増え、空き家問題が広がってくる中で、ようやく住む人が自らプーイヤーとして、住居のデザインに参加できる社会背景が整ってきたのだと思います。
つまり、住む人たちの「この家をこうしたい」「自分らしい住まいにしたい」というニーズは実は潜在的にずっとあったニーズであり、それが最近になってようやく具現化し始めたのです。
本田:入居者との関わりの中で、プロとしての目線と、実際に住む人々の「素人目線」の間にあるギャップに気づかされるという点は、非常に大切なポイントだと感じました。これは、入居前の不動産担当者による案内時や入居後のトラブル対応、さらには退去時に得られるフィードバックなど、限られた機会の中で入居者のニーズをどう汲み取るかが鍵になります。
これらの「タッチポイント」を通じて、住む人がどのようにその空間を利用しているのか、また自分たちの想定と実際の利用法にどのようなズレがあるかを理解することは、今後のデザインやリノベに反映させるために非常に重要な現場の知見です。
賃貸リノベでは、入居者の顔が見えず具体的な要望がない場合でも、入居者がどのようにその空間を使うのかを想像し反映する必要があります。まさに、「顔が見えない人のために空間を作っている」ということになります。だからこそ、ビジョンやターゲット、コンセプトを部屋ごとに考え、そのフィードバックを次のプロジェクトに活かす姿勢は非常に重要です。
信濃:「入居者に使い方を委ねる」というスタンスは、現代の住まい方に非常にマッチしているように思います。特に、空間に余白や柔軟性を持たせることで入居者が自由にカスタマイズできるという点は、今のニーズに合っているのではないでしょうか。
例えば曖昧な境界線や用途が決まっていない空間を提供すると、入居者は「どう使おうか」というワクワク感を感じることができます。従来のように各部屋の用途を明確にするよりも、可変性を持たせた方が、住む人のクリエイティビティを引き出し、結果的に住み心地が良くなるというのは、まさに現代的なアプローチです。
――そういったリノベーション物件に実際に入居してもらうためには、やはり「共感」が大事なキーになるのでしょうか?
本田:共感は非常に重要なテーマですね。特に仲介業者の役割が大きく、物件を案内する際にその物件の特徴やコンセプトを深く理解し、入居希望者にうまく伝えることができるかどうかが入居を決める鍵になると思います。
仲介業者が物件について何も知らなければ入居希望者は共感を得ることができず、結果として契約に至らない可能性が高くなります。一方で、物件のビジョンや設計者の意図を丁寧に説明することで、入居希望者の「この物件に住みたい」という共感を得ることができます。
また、リノベ物件やデザイン性の高い物件では入居者自身がその設計者の意図を読み取り、さらには共感している場合もあります。例えば「玄関に靴箱がないのは、靴を玄関に置かないという設計者の意図なのだろう」と深読みし、そのとおりに生活する入居者がいるという話は、まさに設計者、オーナー、管理会社、そして入居者が一つの「共感の輪」を形成していることを示しています。
共感が生まれると物件の価値がより高まり、多少家賃が高くてもその価値を認める入居者が増え、結果的に物件の魅力がさらに引き立つという良い循環が生まれます。これは物件を提供する側だけでなく、入居者にとっても「自分らしい生活」を実現するための大切な要素となります。
――この共感の輪を築くことができるかどうかが、物件の成功に大きく影響するというのは重要なポイントですね。
信濃:かっこいいデザインを「パッと作った」だけでは、住まいの魅力を最大限に引き出すことはできないと思います。特に山王マンションのように歴史や背景を持った建物では、その「歴史」や「魅力」を理解し語れる人が必要であり、その価値を入居希望者にしっかり伝えることが大切です。そうしたプロセスがあるからこそ、入居者も物件に共感し、魅力を感じるのです。
(2025年1月公開)
【電子版連載】次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー:特別座談会(2)へ続く