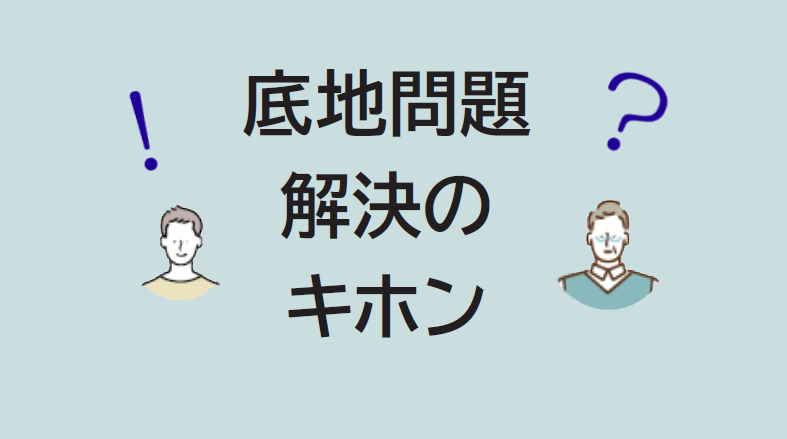賃貸住宅で土地活用を考える際、最初に思い浮かべるのは木造アパートではないでしょうか。実際、国土交通省が発表した「建築着工統計調査報告(令和6年計分)」の「住宅着工統計」によれば、2024年に着工した賃貸住宅(貸家)34万2092戸のうち、最も多い40%にあたる13万7071戸が木造でした。
ここでは木造の押さえておきたい基礎知識を紹介しつつ、木造の賃貸住宅を建てる際のメリットとデメリットを解説します。
木造の工法や耐用年数をおさらい
工法は大きく分けて「木造軸組工法」と「2×4工法」の二つ
柱や梁など、建物の主要な骨組みに木材を使用しているのが木造建築物です。その工法は大きく分けて「木造軸組工法」と「ツーバイフォー(2×4)工法(木造枠組壁工法)」の2つに分けられます。
木造軸組工法は「在来工法」とも呼ばれる日本の伝統的な工法です。建物の縦・横・斜めをそれぞれ柱・梁・筋交いなど「線」でつないで支える造りとなっています。大きな開口部を造りやすく間取りやデザインの自由度が高い、リフォーム・増築がしやすいといったことが特徴です。

一方、北米で生まれた「ツーバイフォー工法」は、木材でつくった枠に壁や床などをはめ込み「面」で支えます。枠組みに使用される木材が約2インチ(約3.8cm)×4インチ(約8.9cm)と規格化されていることから「2×4(ツーバイフォー)」という名が付きました。床、壁、天井から成る箱のような六面体で支えるため、耐震性や耐久性が高いほか、枠組み材が空気の流れを遮断することから防火性が高いのも特徴です。ただし、構造を支える面のサイズが決まっているため木造軸組工法よりも間取りの自由度が低く、大がかりなリフォームがしにくい側面もあります。
法定耐用年数は22年だが、100年超使い続けることもできる
国税庁によれば、木造建物の法定耐用年数は表のとおり。
●木造・合成樹脂造のものの耐用年数
| 細目 | 耐用年数 |
| 事務所用 | 24年 |
| 店舗・住宅用 | 22年 |
| 飲食店用 | 20年 |
| 旅館・ホテル・病院・車庫用 | 17年 |
| 公衆浴場用 | 12年 |
| 工場・倉庫用(一般用) | 15年 |
(出典・国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」を基に地主と家主で作成)
法定耐用年数はあくまで減価償却費などの計算に用いるために定められた数値です。
減価償却費は「減価償却費 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数」で計算します。木造建物の償却率は「0.031」、経過年数は築年数ではなく所有期間です。なお、所有期間が1年未満の場合は、6カ月以上であれば1年として計算し、6カ月未満は切り捨てます。
一方で、使用状況によって異なりますが、木造建物の一般的な寿命は50~60年程度とされています。また適切に修繕したりリフォームしたりすることで100年以上使い続けることも可能です。

賃貸住宅を木造で建てる最大のメリットはコストの低さ
低コストを実現する理由は資材価格と工期
賃貸経営を考える際、避けては通れないのが利回りの確保です。だからこそ鉄骨造やRC造と比べ建築コストが低いことは、木造の最大のメリットといえるでしょう。
木造がほかの構造よりも建築費を抑えられる理由の一つは、材料費が安価な点です。建築着工統計調査報告(令和6年計分)の住宅着工統計で、1㎡あたり工事費予定額を構造別で見てみると木造が最も安いことが分かります。
●主な構造別1㎡あたり工事費予定額
| 構造 | 予定額 |
| 木造 | 20万円 |
| RC造 | 32万円 |
| 鉄骨造 | 31万円 |
(出典・建築着工統計調査報告(令和6年計分)住宅着工統計を基に地主と家主で作成)
ただ、木材の価格は注視が必要です。新型コロナウイルス禍やロシアのウクライナ侵攻を受けて発生した「ウッドショック」はある程度落ち着いてきたものの、原油価格の高騰やアメリカの関税政策の影響を受けて不安定な状況が続いています。

低コストを実現するもう一つの理由が工期の短さです。大手ハウスメーカーでは「階数+1カ月」が目安とされています。規模によって変わるものの、余裕をもって4~6カ月程度と見ておくといいでしょう。工期が短くて済むということは、その期間に職人に支払う人工代も安く済むのです。職人不足が指摘される昨今、これは大きなコストカットにつながります。
自由設計できるデザイン性の高さもメリット
木造アパートの魅力はコストだけではありません。デザインの自由度が高いため、ほかの賃貸物件と差別化しやすい点も多くの家主に選ばれる理由の一つです。特に、柱と梁の組み合わせで広々としたリビングや吹き抜けをつくれる木造軸組工法であれば、将来的に大きく間取りを変えることも可能です。築古アパートの価値を向上させることができるでしょう。
木造アパートのデメリットと言われる「音」と「火」は技術でカバー
技術の進歩で音の響きを軽減
木造アパートで気になるのは、やはり遮音性の低さではないでしょうか。「木造は音が響く」というイメージを持っている人も多いかもしれません。
確かに、木材はコンクリートなどと比べて振動しやすいため、音が響きやすいとされています。しかし現代では、壁に入れる遮音シートや二重に貼る石こうボードなど、音が伝わることを防ぐ資材が多数開発されています。そうした対策をすることで遮音性を高めることが可能です。

防火地域には建てることができない
耐火性の低さも木造のデメリットの一つです。木が燃えやすいことは仕方のないことですが、すでに難燃処理を施した燃えにくい木材が登場しています。また、構造部分の主要な木材を石こうボードなどで覆う「メンブレン型耐火構造」や、耐火被覆材やモルタルなどで燃え止まり層をつくる「燃え止まり型耐火構造」など、耐火性能を高める方法もあります。
ただし、都市の中心部で建物の密集度が高い「防火地域」では、木造アパートを建てることはできません。不燃材を用いることで基準をクリアできるケースもありますが、その分のコストがかかってしまいます。
寒さの原因は気密性の低さ
木造と聞くと寒い部屋をイメージする人もいるでしょう。しかし実は、木材は熱を伝えにくいため断熱性能が高いのです。では、なぜ寒く感じるのかというと、気密性が低いからです。つまり気密性を高めれば、夏は涼しく冬は暖かい室内環境をつくることが可能です。窓のサッシやドアに気密性の高い商品を選び、気密テープやパッキンで隙間を埋めるなどすることで、木造にありがちな隙間風のない、快適な室内をつくることができます。
木造のメリット・デメリットを知って、納得のいく賃貸経営を
低コストでアパートを建てることができる木造。自由にデザインできて、将来的にリフォームがしやすいことも魅力です。木造であれば土地の広さを問わず、家主の予算や希望に沿った賃貸物件を建てやすいといえそうです。
一方で、防火地域には基本的には建てられませんし、遮音性、気密性を高めるためには対策が必要になるといった注意点もあります。
賃貸経営は、入居者が長く住むことで安定します。そのためには室内の快適性の確保が重要です。納得のいく賃貸経営を実現するために、木造のメリットとデメリットを理解しておきましょう。
(2025年10月17日更新)

 100%紙製のAED収納ボックス -森紙器
100%紙製のAED収納ボックス -森紙器 賃貸物件便利アイテム -ウォールバー
賃貸物件便利アイテム -ウォールバー