最終回 変わりゆく損保業界のスタンスについて考える⑩
これからの損害保険業界④
大手損害保険会社と副業大型乗合代理店の、ゆがんだ関係が引き起こした数々の不祥事をきっかけに、損保業界全体が大きく変わろうとしています。
不祥事を生んだ背景にあった双方のもたれ合い体質を解消するために、損保会社には毅然きぜんとした態度、代理店には自立が必要とされています。これは業界全体が一様に求められている、本来あるべき姿なのです。
では、これにより賃貸不動産業界においては今後どのような影響があるのでしょうか。
損保会社の庇護の下、増え続けてきた副業代理店
2023年の統計※によると、損保代理店数および保険募集従事者数のいずれも80%以上が、実は副業代理店です。最も多いのは自動車関連業(自動車販売店、自動車整備工場)ですが、次いで多いのが金融業(銀行など、銀行などの子会社、ノンバンク、生命保険会社)、不動産業、建設業などの不動産賃貸業に縁の深い業種の副業代理店です。つまり家主は、かなりの割合でこれら副業代理店と火災保険、賠償責任保険などの損保商品の契約を締結していると思われます。
前回話したとおり、副業代理店は自主独立した代理店経営形態に転換していかなければなりません。保険設計、契約管理、顧客管理、事務処理、事故処理など、これまでは損保会社からの出向社員が代行していた代理店も相当数あったと思われます。損保会社に頼り切っていたこれらの業務を、すべて自力で行なうことは簡単ではありません。
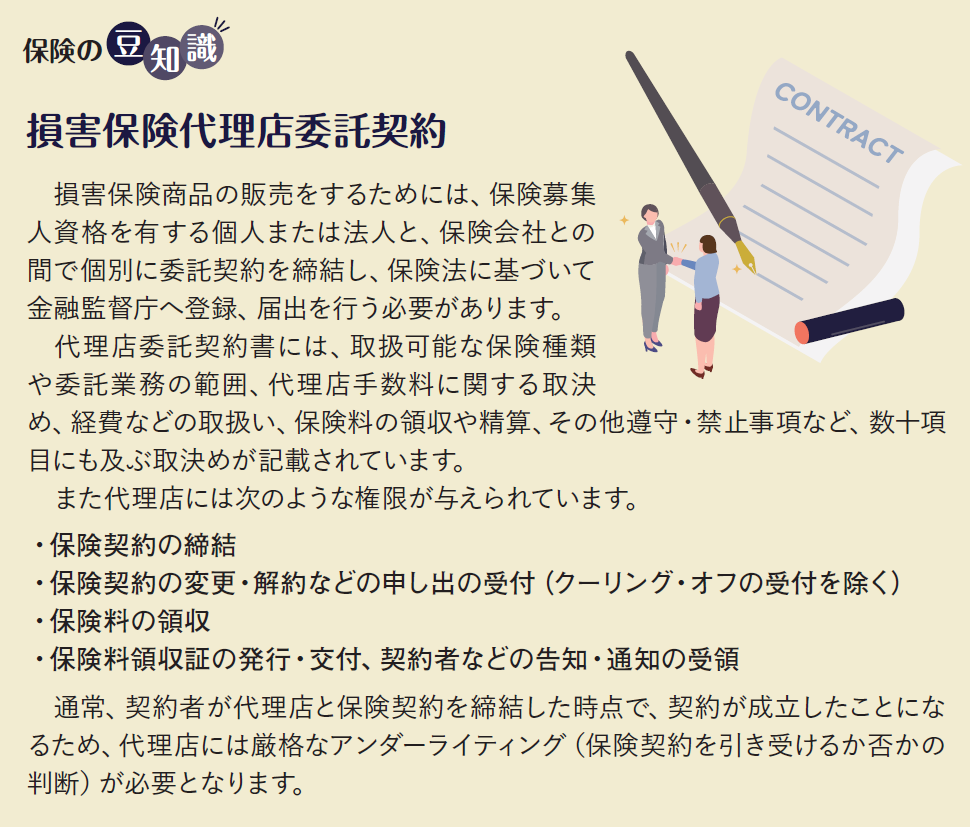
特に賃貸不動産経営の分野における保険設計、事故処理は特殊性が高く、不動産賃貸業と保険の両方を理解した、専門的なスキルが必要です。専業代理店であっても手を焼くこれらの業務スキルを、副業代理店が直ちに身に付けることができるのか、注目すべきではないでしょうか。 ※一般社団法人日本損害保険協会の統計データ
副業代理店や企業内代理店の淘汰が進む可能性
副業代理店や企業内代理店が、代理店としての高い業務水準をすべて自力で確立し、従来どおりの高い手数料率を獲得することは、至難の業だといえるでしょう。出向社員に代わる人材の確保・育成、その他の業務コストも増大することは間違いありません。そうなると、収益を見込めなくなった副業代理店が、廃業や事業譲渡を検討することも多くなると思います。
その対応策として、大手損保会社では本来代理店が委託を受ける業務の一部を、損保会社のグループ会社などに移管させる制度を導入する動きもあります。つまり専門スキルが必要な保険業務に手をかけたくない代理店は、新規顧客の獲得に専念し、保険設計や契約業務、メンテナンスは損保会社またはグループ会社が分担するというものです。これによって代理店手数料は半減するケースもあるそうですが、煩雑な業務をアウトソーシングできるメリットがあります。
一方で、契約者にとっては面識もつながりもない代行会社の、その都度違う担当者とやりとりしなければならなくなるかもしれません。家主という事業を理解してもらい、うまく意思の疎通が図れるのかが課題です。
また複数の損保会社、保険商品を比較しづらくなるのも確かでしょう。本来ならそのアドバイスは乗合代理店がしていたわけですから、家主自らが保険商品の選定、最適な補償プランを理解してオーダーしなければ、必要十分な保険設計はできないかもしれません。
以前の連載『家主のための保険虎の巻』から引き続き、合計106回、約9年の長きにわたり執筆を担当してきましたが、今回が最終回となります。
保険業界歴36年、家主歴24年の「大家さん専門保険コーディネーター」が知り得る、賃貸不動産経営に必要な保険の知識、経験、情報を、読者の皆さんに惜しみなくお話ししてきたつもりです。
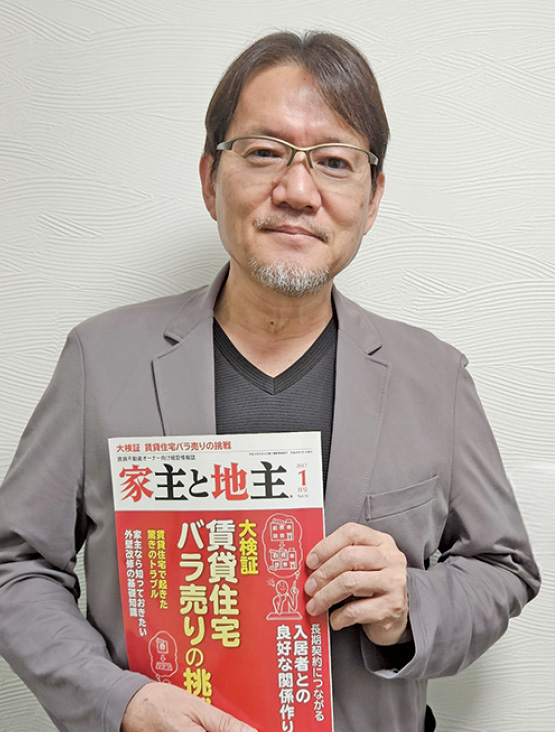
家主向けの保険を学ぶ場所も機会も、残念ながら多くはありませんが、これからますます、家主として保険に関するスキルアップが必要な時代に、これまでの記事がテキストのような存在になれたらうれしく思います。長い間ご愛読いただき、誠にありがとうございました。
【解説】
保険ヴィレッジ 代表取締役 斎藤慎治氏

1965年7月16日生まれ。東京都北区出身。大家さん専門保険コーディネーター。家主。93年3月、大手損害保険会社を退社後、保険代理店を創業。2001年8月、保険ヴィレッジ設立、代表取締役に就任。10年、「大家さん専門保険コーディネーター」としてのコンサルティング事業を本格的に開始。
(2025年 10月号掲載)





