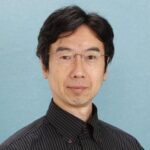- HOME
- 賃貸経営
- リフォーム・リノベーション
- 【電子版連載】次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー:特別座談会(4)
「場のデザイン」から「共感不動産」を考える
【電子版連載】次世代不動産経営オーナー井戸端セミナー:特別座談会(3)に続き、第二弾カレッジ「場のデザインから共感不動産を考える」を総括して、九州産業大学准教授・信濃康博氏 、スペースRデザイン・本田悠人氏、𠮷原勝己オーナーの3者で実施した座談会をレポートする。
- 九州産業大学 建築都市工学部 准教授 信濃康博氏
- スペースR デザイン(福岡市) 本田悠人氏
- 𠮷原勝己オーナー(福岡市)
***リノベーションが担う「共感」は次の時代へ***
――20年前と比べると「リノベーション」という言葉も一般化してきたと思いますが、長年リノベを手掛けられている中で、変化を感じたことなどはありますか?
𠮷原:リノベが登場した当初は、マイノリティー的なカルチャーとしての吸引力がありましたよね。もともと古い建物や場所に対して新しい価値を見出し、「普通ではないもの」を楽しむという感覚が、リノベの文化の根本にあったと思います。当初は反主流的なものとして、リノベがある種の「反戦活動」的なエネルギーを持っていたという指摘も非常に鋭いです。
ところが、今やリノベは一種の「普通名詞」になり、広く一般化される中で、かつてのような「マイノリティーのカルチャー」としての吸引力を失いつつあるのかもしれません。つまり、かつてリノベに惹かれていた人々は、強い共感やこだわりを持って集まってきましたが、今ではリノベそのものが広く認知され、かつ多様化した結果、「リノベーション」という言葉自体がもはや特別感を失いかけているという現象が起きているのです。
そうすると、リノベが再び新しい意味や価値を持つためには、単なる空間改修を超えた「体験のデザイン」が求められます。それが、現代の多様化した共感社会において、新しいリノベの道を切り拓く鍵になるのではないでしょうか。
信濃:お話しの通り、次のステップとして、与えられたものに共感するだけでなく自分でつくり上げていくプロセス自体に共感を見出す時代が来るのではないかと思います。消費傾向が、単なる受け手の立場から、より「自己実現」を求める方向にシフトしていく兆しが強まっていますよね。
スケルトンに近い状態で自由度を高くし、住む人や使う人が自ら手を加え、カスタマイズできる要素を残しておくというのは、まさにその流れに合致しているように感じます。自らの選択や手仕事が反映された空間こそが、最終的には一番強い共感や満足感を生むものになります。それは、ただの「共感」ではなく、「自己実現」に近い内発的な価値を生み出す場となるわけです。
この「内発的な価値」を生み出す空間が、これからの人々のニーズに合ったものになるという視点は非常に重要で、この先のリノベや空間デザインの新しい方向性として大きな可能性があると感じます。
本田:最近では、新築マンションや住宅もリノベの要素を取り入れることが増えてきましたね。「リノベっぽい新築」が、まさに新しいトレンドになりつつあります。それは、単なる「新しい空間」を提供するのではなく、「自分らしく暮らすための土台」をつくるという方向に進化しているからだと思います。今後、ますますリノベの持つ「自由さ」や「個性」が新築に反映されていくでしょうし、それに伴って住む人が自分の空間を積極的につくり上げていく文化も、より広がっていくのではないでしょうか。
𠮷原:リノベには「民主化」と「ボーダレス化」という二つの大きなテーマがあると思います。ここ20年で、不動産業界全体で起こってきた変化の一つは、賃貸や住空間の「民主化」です。つまり、かつては限定的だった空間の使い方や選択肢が、より多くの人に開かれるようになり、入居者が自分の手で空間をつくり上げられるようになりました。それと同時に、「ボーダレス化」というのは、住空間においての柔軟性を示していて、従来の固定的な住まいの概念を超えて、より自由で境界のない空間づくりが進んできたことを指していると思います。
リノベ文化は、そうした時代の流れや市民のニーズに応える形で進化してきたと言えますね。DIYやSOHOを許容する空間は、まさにその「民主化」と「ボーダレス化」を体現している例でしょう。
信濃:昭和から平成、そして現在に至るまで、不動産に対する考え方は大きく変わってきました。今後、不動産の価値がどのように変わっていくのか、本当に不確実な時代に入っていますが、そうした時代だからこそ、リノベのように柔軟に対応できる空間づくりがますます重要になっていくのだろうと思います。
𠮷原:今回のテーマである「場のデザイン」と「共感不動産」に立ち返ると、単に物理的な空間や場を提供するだけでは不十分だという結論に至りますね。新築物件がリノベのデザインやアイデアを取り入れてきていますが、それでもなお、リノベ物件には新築にはない特別な魅力があると皆さん感じていると思います。その違いの本質は、やはりリノベ物件には「人の痕跡」や「手垢」が見え隠れしているからこそ、強い共感を生むのではないかと感じます。
リノベされた築古の物件には、長い歴史やかつて住んでいた人々の「物語」が詰まっています。単なる新しいデザインや綺麗さではなく、そこに込められた人の感情や経験が、その空間にいる人に共感を生む要素として働いているのです。たとえ同じようなデザインや機能を新築で提供したとしても、その「人の物語」や「積み重ね」がないと、やはり同じ共感は得られないのだと思います。
となると、これからの「場のデザイン」は、ただ空間の美しさや機能性だけを追求するのではなく、そこに関わる人々のストーリーや存在感を感じさせることが重要になってきます。つまり、場そのものだけでなく、その場をどう使い、どう共につくり上げていくかが、デザインの一部として考慮されなければならないということです。リノベはその点で、物理的な空間だけでなく、そこでの人々の暮らしや関わり合いをデザインすることが重要な役割を果たしてきたわけです。
信濃:素材そのものが持つ「劣化」や「変化」を受け入れ、それをオペレーションの一部に組み込むというのも非常に重要な要素だと思います。例えば、鉄が錆びる過程や木材が古びる過程、それ自体が時間の経過と共に美しさを増し、建物全体の魅力として機能する。それは単なる「経年劣化」ではなく、「経年美化」とも言える現象です。これを意図的に設計に組み込むことが、長期的に住む人々との共感を生むポイントになっているのだと思います。
本物の素材を使うことで、その素材が経年変化していく様子を住む人たちと一緒に見守り、手を加え、修繕する。それが「共感」を生む大きな要素だというのは、非常に共感できます。自然素材や金属の変化は、時間が経つほどにその場所に「物語」が蓄積されていく感じがします。
ヨーロッパの街並みや、長い歴史を持つ建物に人々が魅力を感じるのも、まさにこの「経年美化」と言える部分に価値を見出しているからだと思います。それは新築では得られない、一種の「時を重ねることによる価値」のようなもので、その点において、リノベは新築とは全く異なる魅力を持っています。
𠮷原:山王マンションのエントランスや1階の部分に見られる鉄の錆び具合なども、その建物の独特な魅力を際立たせています。また、木材を使った柱の目隠しも、定期的に塗り直さないといけない手間があるけれど、それ自体が一つの「楽しみ」となる。このような「手間」をかけることがむしろ住む人たちとの関係性を深め、共感を育むプロセスになっているのが非常に興味深いです。
その意味で、リノベにおける素材の選択やその後の維持管理、さらにはそれに伴うオペレーション自体が、長期的でサステナブルな共感を生むための大切な要素となっているというのが、まさにこれからのリノベデザインの鍵になるのではないかと感じます。
これからの場のデザインは、場に込められた物語や歴史、住む人々がどうその空間に手を加え、どう暮らしていくかを含めた「共創のデザイン」がますます重要になる時代になっていくのだと思います。
本田:リノベの持つ「手間」や「不完全さ」が、逆にコミュニケーションや共感を生むきっかけになっているという面もあります。新築物件とは異なり、リノベ物件は完璧な状態ではないことが多く、その「不完全さ」や「トラブル」が、入居者と管理者、施工者との間にオペレーション的なやり取りを生み出します。その結果、入居者がその物件に愛着を持ったり、管理会社がより密接に入居者と関わる機会が増えたりするのは、まさにリノベならではの特徴だと思います。
この「オペレーション」自体が、リノベの価値の一部であり、それを積極的に活かすことができるかどうかが鍵ですよね。新築物件の場合は完璧な状態が前提なので、トラブルが起きるとクレームに直結しますが、リノベ物件では「改善」や「改良」という名目で、むしろ入居者とのコミュニケーションが深まる。それが、入居者にとっても管理者にとっても「一緒に空間をつくり上げていく」プロセスとして楽しめる要素になっているのではないでしょうか。
𠮷原:オペレーションを意図的に設計に組み込むというのも面白い発想ですよね。例えば、物件自体にある程度の「手間」を残しておくことで、入居者と管理者の関係を持続的に保ち、トラブルや改善を通じて一緒に空間をつくり上げていくという方法です。これは、入居者が単なる「消費者」としてではなく、空間の「共創者」として関わることを促進します。
実際の例としては、オープンスペースや共有部分を設計段階であえて手をかけずに残しておいて、入居者やコミュニティーと一緒にそのスペースをどう活用するかを決めていくことが挙げられるかもしれません。こうした設計は、「完璧な空間」を提供するのではなく、「発展途上の空間」を提供し、入居者がその過程に関与することで、より強い共感や愛着が生まれるという仕組みです。
本田:リノベが「オペレーションの一環」として捉えられるという視点は、まさに今後の場のデザインにおける新たな挑戦ですね。住む人や使う人が時間をかけて共につくり上げていくプロセス自体が、その空間の価値を高め、同時に管理者との継続的な関係を築いていく手段になる。これは新築ではなかなか得られないリノベの醍醐味だと言えるでしょう。
𠮷原:確かに、これからの不動産や空間デザインの主役が「場を提供する側」だけではなく「その場を活用する人々」へとシフトしているというのは、大きな変化だと思います。特に共感をベースにした不動産という概念が広がっていく中で、空間そのものよりも、空間とその人々をつなげる「関係性のデザイン」が非常に重要になってきています。
今までは、空間の設計や設備が整っていれば、それが賃貸の価値を決定する大きな要素だったかもしれません。しかし、今の時代では、空間を「どう使うか」、さらには「どう自分なりにアレンジできるか」という点に重点が置かれるようになってきています。これは、「提供される完成された空間」よりも、「自分で手を加えて育てていける空間」に価値が移っているということです。
信濃:ここで、本田さんのような案内やアドバイスができる存在が極めて重要になります。単に空間を紹介するだけでなく、その空間を「どう活用できるのか」を一緒に考え、時には具体的な提案やサポートを提供することで、住む人々にとってその空間が特別なものになります。つまり、単に物件を案内するのではなく、その場の「可能性」や「使い方」を提示し、入居者がその場に自分なりの価値を見出すためのサポーターになるということです。
これによって、場の価値が「物理的な場所」から「体験や関係性」へとシフトし、住む人自身がその空間に対して愛着を持ち、長期的な関わりを持つようになります。さらに、その空間での経験を自分なりにアレンジしていく過程で得られる満足感や自己実現の感覚が、その人にとっての大きな価値となるでしょう。
不動産や空間デザインの未来では、場を提供するだけではなく、その場での体験や関わりをどうデザインするかが重要になり、住む人と「一緒に空間を育てていく」という考え方が主流になっていくのではないかと思います。これは従来の「設計者やオーナーが主役」という構図から、「住む人や使う人が主役」であり、彼らが空間をどう使い、どう変えていくかを見守り、サポートする存在が必要な時代へと変わっていくことを意味しているのではないでしょうか。
𠮷原:手間をどう捉えるか、つまりそれを「手間」と見るか、「価値を生むプロセス」として考えるかという視点の違いが、リノベデザインにおける大きな分かれ道だと思います。あえて「手間」をかけることで、住む人との関わりやオペレーションが生まれ、結果として長期的な賃料の上昇につながるのは、非常に興味深い視点です。
信濃:山王マンションなどの事例は、すでにブランディングが確立されているわけですが、その中で「手間をかける」ことが、単なるコストではなく、リノベデザインの核心に位置づけられているというのが面白いですね。住む人がその場所に愛着を持ち、自分自身の手を加えながら空間を育てていくというプロセスが、最終的に高い価値を生む。そして、その価値が賃料にも反映されるというサイクルは、まさに「手間をかけることの意義」を証明していると思います。
𠮷原:究極的には、新築とヴィンテージビルの違いにおいてヴィンテージビルの方が賃料が高くなるという現象も、これからより顕著に見られるかもしれません。ヴィンテージビルが持つ「歴史」や「手垢」のようなもの、つまりその場に宿る物語や人の関わりが、住む人にとってより深い価値を感じさせるからです。新築が提供する「完成された空間」に対して、ヴィンテージビルは「まだ育てていける余地のある空間」であり、住む人自身がその価値をつくり上げていけるという魅力が大きな要因となっているのではないかと思います。
これからのリノベデザインは、まさにこうした「関係性のデザイン」を重視する方向に進んでいくのかもしれません。
(2025年2月公開)
次週公開の記事(5)へ続く