第45回 変わりゆく損保業界のスタンスについて考える⑤
保険契約の引き受け制限③
シェアハウス、太陽光発電事業、コインランドリー、民泊など、不動産賃貸事業から派生する投資対象にはさまざまなものがあります。
不動産賃貸経営の経験をある程度積んだ人が、さらなる収益拡大を目指して参入するケースが多いかと思います。
ところが、これらは決して賃貸不動産経営の単なる延長ではない、それぞれ特有のリスクがある別分野の事業なのです。そのハード面のリスクに効果的に備えることができるのが損害保険ですが、ここにも損保業界は契約引き受け制限を設けるようになりつつあります。
今後その分野への参入を検討している、またはその事業を続けようとしている人は気にしておかなければならない、損保業界の動向について説明したいと思います。
築古戸建てからの転用が多い シェアハウス

一般的なシェアハウスは、リビング・ダイニング・キッチン(LDK)、バス、トイレなどの共有スペースを中心に、入居者の専有スペース(居室)が複数存在する構造になっています。つまり、普通の一戸建てと基本的には同じ造りになっています。玄関(入り口)は通常一つか二つですが、火災保険を掛ける場合の取り扱いは「共同住宅」として引き受けます。そしてアパートなどと同様、築年数による引き受け制限が設けられています。
事前に建物ごとに個別審査が必要で、引き受け可能な場合であっても、高額な免責金額(10万円以上)の設定、保険期間は1年に限定、破損・汚損条項、費用保険金特約などの補償を不担保とするといった条件が付けられます。
シェアハウスは、築40年を超えるような超築古戸建てなどを転用するケースが多いため、室内のリフォーム、リノベーションだけでなく、同時に屋根や外壁などの外装の修繕工事も施しておかないと、火災保険に加入できない事態もあり得ます。そのことを考慮して、開業のための予算を立てるべきではないでしょうか。ちなみに、築40~50年以上の物件の契約を一切引き受けない保険会社もあります。
太陽光発電設備で多発する 送電ケーブル盗難被害
不動産賃貸事業の次の投資対象として、太陽光発電事業に興味を持つ投資家も多いことでしょう。空室リスクがないこと、手間がかからないことなどがその理由のようですが、台風などの自然災害により設備が受ける被害、それに伴う売電利益損失の発生が深刻な状況です。
これに加えて、昨今では地下に埋設、または敷設されている送電ケーブルの盗難被害が後を絶たず、火災保険、利益損害補償保険とも収支が非常に悪くなっています。
そのような事情から、現在太陽光発電設備は「高損害率業種」に分類されており、新規の保険契約引き受けには損保各社とも極めてネガティブです。原則事前申請が必須となっており、設置状態、周辺環境などが良好であること、過去に大きな事故歴がないことなどが条件とされています。その審査基準はとても厳しいもので、契約の引き受けがかなうケースのほうが少ないくらいです。
継続契約であっても、事故が複数回発生していると、次回の契約を引き受けないか、数十万~数百万円単位の高額な免責金額の設定が条件となる場合があります。
安定的な投資対象として一世を風靡(ふうび)した太陽光発電事業は、保険という重要なリスクヘッジの手段が失われつつあると言わざるを得ません。
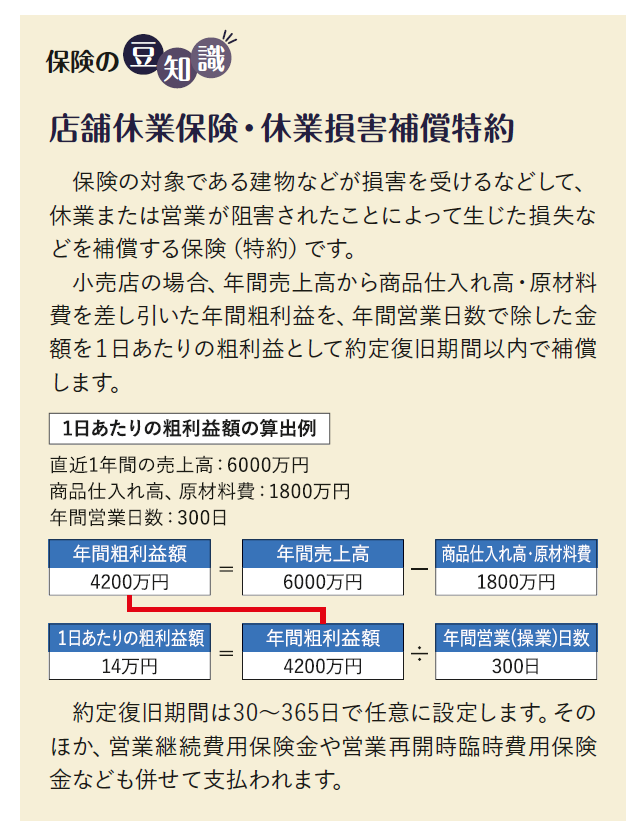
【解説】
保険ヴィレッジ 代表取締役 斎藤慎治氏

1965年7月16日生まれ。東京都北区出身。大家さん専門保険コーディネーター。家主。93年3月、大手損害保険会社を退社後、保険代理店を創業。2001年8月、保険ヴィレッジ設立、代表取締役に就任。10年、「大家さん専門保険コーディネーター」としてのコンサルティング事業を本格的に開始。
(2025年 5月号掲載)





